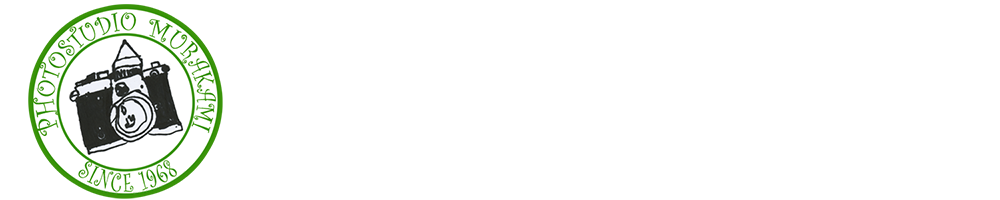昆虫写真家 ムシ男

昆虫写真家 ムシ男(ムシオ)こと村上幸隆です。
スタジオ経営の傍ら、ライフワークとして、商品撮影事務所で学んだ撮影技術を活かした世界のカブトムシ・クワガタを撮影し始めて約20年になります。
きっかけは、2003年ごろから流行り始めたトレーディングカードゲーム「ムシキング」です。
わが息子もその影響を受けた1人で、
「カブトムシ、クワガタムシの写真を撮影して!」とよくせがまれました。
その結果、私の方がハマってしまい、現在に至っています。
私が子どものころは、図鑑でしか見ることができなかった世界のカブトムシ、クワガタ。
それが目の前で動いていることに感動します。
ムシ男のこだわり
ライティングのこだわり
カブトムシ、クワガタはエナメル質の為、種類によっては光が当たると白く反射し質感が失くなってしまいます。
そのようになって魅力が半減してまわないように、それぞれの昆虫の状態に応じて細心の注意を払い、ライティングを行っています。

ポジションのこだわり
カブトムシ、クワガタはそれぞれの個体が個性豊かな色、形をしており大変魅力的です。
その魅力を表現するために撮影する昆虫たちをよく観察し、カメラアングルを決めて撮影しています。

色の再現へのこだわり
カブトムシ・クワガタは、個性豊かな色を持ち合わせています。
これらの色を写真に収める為に、撮影環境には特に注意をしました。
ちょっと専門的になりますが、カメラ設定をRAW設定、使用するそれぞれのストロボの色温度を合わせて、色かぶりや濁りを抑えることで昆虫の色に影響が出にくいようにしています。

撮影の心得
昆虫のストレスを抑えるために

- できる限り触れない
- 短時間で撮影する
- ライトは離す
- 駆け引き
- 性格を観る
- 対話しながら
- 隠れたら終了
昆虫の撮影時は「可能な限り昆虫への負荷を抑える」事が重要です。
そこで、ライトは昆虫から離し、できる限り触らないよう注意を払います。
また、人間と同じように、昆虫にも「負けず嫌い」「臆病」「落ち着きがない」など性格も様々です。
まずは性格をよく観察します。
例えば、負けず嫌いの昆虫であれば、逃げずに威嚇します。
臆病な昆虫であれば、すぐに木の裏に隠れます。
特に、気が強い性格の場合は、駆け引きが大事になりますが、どんなに気が強くても危険を感じてしまうと逃げてしまいます。
このような性格を踏まえた上で撮影に入りますが、それでも逃げ出したり、隠れたりすれば、撮影は即終了。
1~2日ほど時間を空け、再び撮影を行います。
このように昆虫と対話しながら撮影を行うことが、より良い昆虫写真を撮るための秘訣です。
以上のような「撮影の心得」を自分自身で決めて、昆虫へ敬意を払いながら撮影しています。

ギャラリー
写真をクリックすると大きな画像でご覧いただけます。
Instagramでも昆虫写真を投稿しています。よろしければフォローお願いいたします。

昆虫への想いと地球への行動
昆虫たちは、私たちが自然を感じたり、学んだり、命の尊さを伝えてくれたりする存在だと感じています。
カブトムシやクワガタは、子どもも大人も関係なく、夢中にさせる魅力ある昆虫です。
私自身がカブトムシやクワガタの撮影をはじめたのも当時5歳の息子からせがまれたことがきっかけでした。
幼い息子たちと昆虫を飼育していく中で、卵から成虫へと変化していく様を見ていて、その大変さを息子たちが理解し始めた頃から、昆虫をとても大事に扱うようになりました。
そのような貴重な体験をさせてくれる昆虫たちを通じて、少しでも興味を持ってもらえればと、国内外のカブトムシやクワガタを撮影するようになりました。
今後の将来を担う子どもたちや若い方々が、昆虫たちを通じて自然環境や地球環境に関心を持ち、未来の地球へ少しでも向きうきっかけになってくれればと願っています。